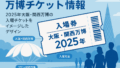暗号資産「105銘柄」に金商法適用へ?最新動向と投資家への影響まとめ
本記事では、2025-11-16時点で報道されている「暗号資産105銘柄への金融商品取引法(金商法)適用方針」について、個人投資家が押さえておきたいポイントを整理します。金融庁は、国内交換業者が扱う主要暗号資産の一部を金商法上の「金融商品」として位置づけ、情報開示義務やインサイダー取引規制を導入する方針を固めたと報じられています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
対象はビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などを含む105銘柄とされ、税制面では株式と同様の20%分離課税の導入も検討中とされていますが、具体的な施行時期や最終的な制度内容はまだ未確定です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
今後は2026年通常国会に向けた金商法改正案の議論が続く見込みであり、暗号資産投資を行う個人としては、法改正の方向性と自分の投資スタンスをあらためて見直すタイミングと言えるでしょう。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
暗号資産「105銘柄」金商法適用方針の概要
現在、日本の暗号資産は主に資金決済法の枠組みで規制されていますが、実態としては「投機・投資対象」として利用されているケースが多く、投資家保護の観点から金商法の枠組みに移行・統合する方向性が議論されてきました。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
報道によれば、金融庁が固めた方針は、国内の暗号資産交換業者が取り扱う銘柄のうち105銘柄を金商法上の金融商品と位置づけるというものです。この105という数字は、日本暗号資産取引業協会(JVCEA)のデータ上、第一種会員が扱う119銘柄のうち、優先して規制対象とする銘柄群と解釈されています(最終的な内訳は現時点で未公表・未確定)。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
金商法の適用に伴い、対象銘柄には情報開示義務とインサイダー取引規制が導入される方向で検討されています。投資家から見ると、「どのようなプロジェクトなのか」「どんなリスクがあるのか」といった情報が、株式や投資信託に近いレベルで整備されていくイメージです。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
この章の要点
- 2025年時点で、暗号資産の一部を金商法の枠組みに移行する方針が示されている(最終決定ではない)。
- 対象は国内交換業者が扱う銘柄のうち105銘柄で、詳細なリストは未公表・未確定。
- 金商法適用により、情報開示とインサイダー取引規制が導入される方向で議論が進んでいる。
金商法適用で何が変わるのか:情報開示・インサイダー規制・税制
今回の議論の中心は、以下の3点です。
- ① 情報開示義務の強化
- ② インサイダー取引規制の導入
- ③ 税制(課税方法)の見直しの検討
情報開示義務の強化
金商法の対象となることで、対象暗号資産については、株式や投資信託のように投資判断に必要な情報の開示が求められる見込みです。報道や公開資料などから、以下のような項目が想定されています。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
- 発行者の有無やプロジェクトの主体(企業・財団・コミュニティなど)
- ブロックチェーン基盤やコンセンサスアルゴリズムなど技術的な特徴
- 価格変動リスク、流動性、主要な取引市場の状況
- IEO等での販売条件や資金調達の経緯
インサイダー取引規制の導入
金商法の対象となると、「重要事実」を知り得る立場にある者が、その事実を公表する前に売買して利益を得る行為がインサイダー取引として規制される可能性が高まります。例えば、プロジェクトの重大な不祥事や、取扱廃止、破産などに関する情報を事前に知り得る人物が、その情報を利用して売買することは違法となる方向です。:contentReference[oaicite:7]{index=7}
税制見直しの「検討段階」
さらに、暗号資産の利益について、現行の雑所得・総合課税(最大55%)から、株式等と同じ20%の申告分離課税への見直しが検討されていると報じられています。ただし、これはまだ与党税制調査会での議論・検討段階であり、決定事項ではありません。:contentReference[oaicite:8]{index=8}
税制の最終的な結論は、今後の税制改正大綱や法案提出のプロセスを経て決まるため、「今すぐ20%になる」と断定するのは早計です。税負担軽減の可能性がある一方で、制度設計によっては別の制限が設けられる可能性もあり、続報を慎重に追う必要があります。
この章の要点
- 金商法適用により、対象暗号資産には目論見書的な情報開示が求められる方向。
- インサイダー取引規制が導入されれば、関係者による不公正取引への牽制が強まる。
- 税制の20%分離課税は「検討・予定」の段階であり、現時点では内容も時期も未確定。
対象となる105銘柄のイメージと国内取引所の状況
現時点で、「どの銘柄が105銘柄に含まれるか」という正式リストは公表されていません。ただし、JVCEAの公表データでは、国内の第一種会員が取り扱う暗号資産は119銘柄とされており、そのうち主要な投資対象として位置づけられる銘柄群が105銘柄として候補に挙がっていると解釈されています(報道ベース・未確定)。:contentReference[oaicite:9]{index=9}
ここでは、実際のリストではなく、どのようなタイプの銘柄が対象になりうるかのイメージを整理するためのサンプル表を示します。
| カテゴリ | 代表的な例(イメージ) | 用途・特徴の例 | 投資家が見るべきポイント |
|---|---|---|---|
| 主要暗号資産 | ビットコイン(BTC)・イーサリアム(ETH)など | 価値保存・送金・スマートコントラクト基盤 | 時価総額・流動性・ネットワークの安定性 |
| レイヤー1/レイヤー2 | 各種パブリックチェーン・スケーリングソリューション | 手数料削減・トランザクション高速化 | 実際の利用状況・開発者エコシステム |
| ユーティリティトークン | 国内取引所上場のサービス系トークン | 手数料割引・ガバナンス参加など | トークンの実需・トークンエコノミクス設計 |
| IEO関連トークン | 国内IEOで発行されたトークン | プロジェクト資金調達・コミュニティ形成 | 上場後の価格推移・実際のプロダクト進捗 |
| ステーブルコイン等 | 法定通貨連動型トークン(取り扱いの有無は事業者次第) | 価格安定を目的とした設計 | 裏付資産の管理方法・発行体の信用力 |
実際にどの銘柄が105銘柄に含まれるかは、今後の金融庁・JVCEA・各交換業者の調整により決まっていくため、現時点では「候補のイメージ」レベルにとどまる点に注意が必要です。
この章の要点
- 105銘柄の正式リストは、2025-11-16時点では公表されておらず未確定。
- JVCEA公表の119銘柄のうち、主要な投資対象が優先的に金商法対象になるとみられている(報道ベース)。
- 今後、公表されるリストや各銘柄の開示情報を確認しながら、保有銘柄への影響をチェックする必要がある。
暗号資産だけでなく、レバレッジを抑えたFX取引も検討したい方は、DMM FXのサービス仕様も確認しておきましょう。
【PR】【DMM FX】について詳しくはこちら個人投資家への影響:メリットと注意点
暗号資産に金商法が適用されることで、個人投資家にとっては「プラス」と「マイナス」の両面があります。
期待できるメリット
- 情報の透明性向上:プロジェクトの中身やリスクが整理され、判断材料が増える。
- 不公正取引の抑制:インサイダー取引規制が機能すれば、極端に不公平な売買が減る可能性。
- 税制見直しの可能性:20%分離課税が実現すれば、長期的な投資を行いやすくなる可能性(あくまで検討段階)。:contentReference[oaicite:10]{index=10}
想定されるデメリット・リスク
- 規制強化による取扱銘柄の見直し:コスト増加や要件強化により、一部のアルトコインが取扱停止・縮小となるリスク。
- 事業者への負担増:交換業者の9割が赤字と指摘される中、規制強化が業界の再編・撤退を招く可能性。:contentReference[oaicite:11]{index=11}
- 短期投機への規制強化:レバレッジ取引や高リスク商品の扱いが制限される可能性。
投資家が今からできること
- 保有している銘柄が国内取引所でどのように位置づけられているかを確認する。
- プロジェクトのホワイトペーパーや公式サイトを読み、リスクを自分の言葉で説明できるレベルまで理解する。
- 税制や規制のアップデートを定期的にチェックし、必要なら税理士等の専門家に相談する。
この章の要点
- 金商法適用は、投資家保護の強化というプラス面と、取扱銘柄縮小などのマイナス面を併せ持つ。
- 交換業者の経営負担増により、業界再編・サービス変更が起こる可能性もある。
- 制度変更を待つだけでなく、自分で情報を取りにいき、リスクを把握する姿勢が重要。
暗号資産のボラティリティが気になる方は、より伝統的な為替市場であるFX取引とのバランスも検討してみると良いでしょう。
【PR】【DMM FX】について詳しくはこちら今からできる準備とリスク管理:暗号資産とFXの使い分け
金商法適用が本格化するまでには、法案提出・国会審議・施行まで一定の時間があります。この「準備期間」を活かし、自分のポートフォリオを見直しておきましょう。
ステップ1:資産配分と目的を整理する
- 暗号資産は「ハイリスク・ハイリターン枠」として、資産全体の何%までとするか決める。
- 短期トレードなのか、中長期保有なのか、目的を明確にする。
- 生活防衛資金や短期で使う予定資金は、暗号資産には回さない。
ステップ2:規制動向を踏まえた銘柄選び
- 情報開示が進む銘柄を中心に、プロジェクトの実態が分かるものを選ぶ。
- 過去の価格推移だけでなく、利用者数や開発状況など「ファンダメンタルズ」も確認する。
- IEO銘柄など、価格変動が極端なトークンへの集中投資は避ける。
ステップ3:暗号資産とFXの役割分担
- 暗号資産:成長性・技術革新を期待した長期投資・テーマ投資。
- FX:主要通貨ペアを中心とした、比較的情報が豊富で流動性の高い市場。
- どちらにもレバレッジを掛けすぎないよう、証拠金・ロット管理を徹底する。
この章の要点
- 金商法適用までは時間があるため、今のうちにポートフォリオの目的と比率を整理しておく。
- 情報開示や規制の進み具合を見ながら、保有銘柄の見直しを行うことが重要。
- 暗号資産とFXはリスク特性が異なるため、役割分担を意識した使い分けが有効。
暗号資産に加えて、規制が整備されているFX市場も活用したいと考えている方は、DMM FXの取引環境やコストも比較検討してみてください。
【PR】【DMM FX】について詳しくはこちらまとめとCTA:制度変更をチャンスに変えるために
暗号資産「105銘柄」の金商法適用は、投資家保護と市場の信頼性向上を目的とした大きな制度変更になる可能性があります。一方で、取扱銘柄や事業者の再編など、投資環境そのものが変わるリスクもあります。
重要なのは、「制度が変わるかもしれないから様子見」だけで終わらせず、情報収集とポートフォリオ管理を通じて、自分なりの投資戦略をアップデートしていくことです。暗号資産だけに偏らず、FXを含む他の資産クラスとのバランスを取りながら、無理のない範囲でリスクを取っていきましょう。
※本記事は2025-11-16時点の公開情報・報道をもとにした一般的な情報提供であり、特定の暗号資産や金融商品への投資を勧誘・推奨するものではありません。実際の投資判断や税務判断については、ご自身の責任で専門家とも相談のうえ行ってください。