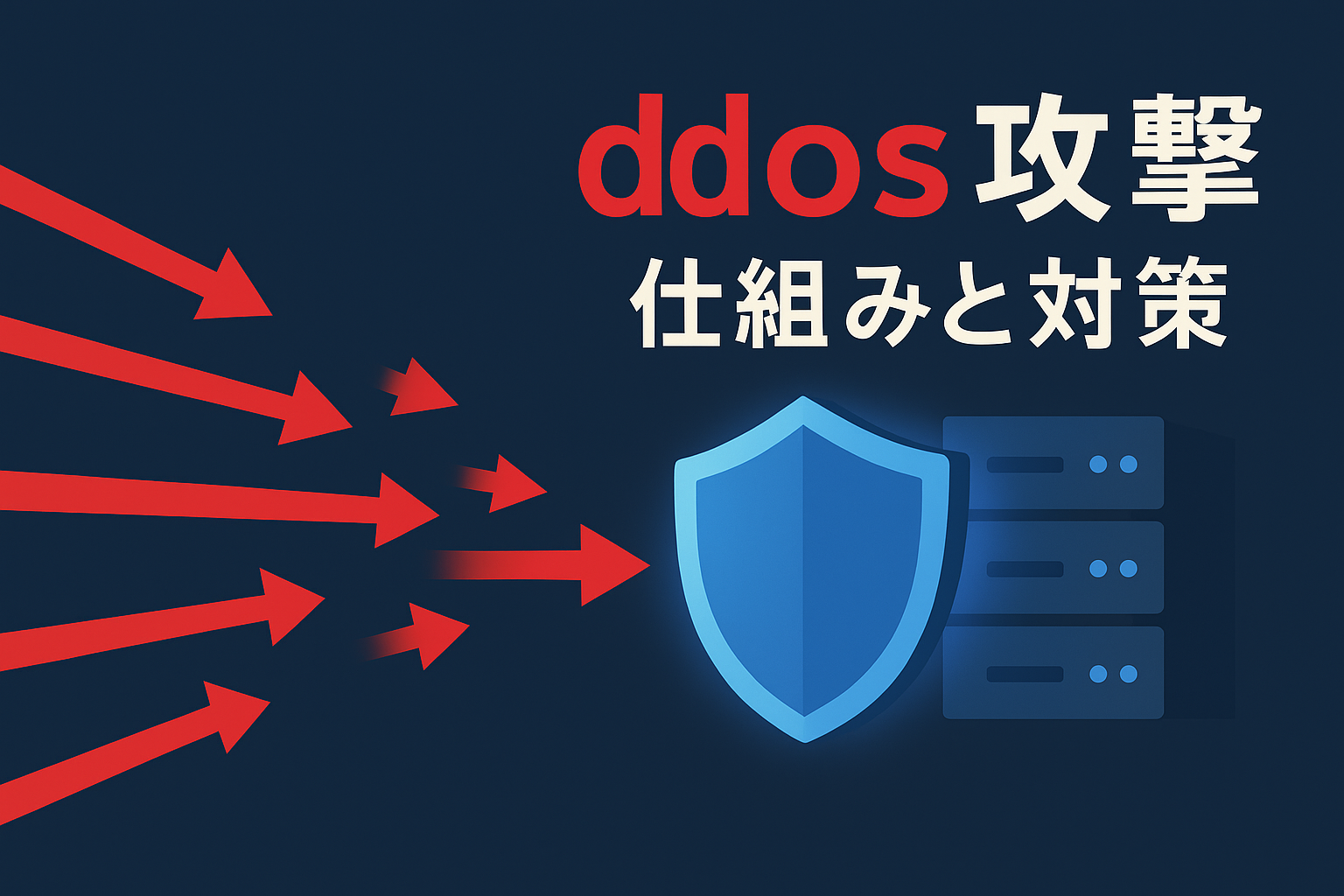ddos攻撃とは何か?仕組みと被害・対策をわかりやすく解説
「ddos攻撃」は企業サイトやオンラインサービスを一気に止めてしまう深刻なサイバー攻撃です。この記事では、ddos攻撃の仕組み・被害・主な種類・対策をわかりやすく整理します。基準日は2025-11-19で、現時点の一般的な情報にもとづき解説しています。
DMM FXでサーバーが安定した取引環境を活用しつつ、資産リスクもあわせて管理してみませんか。
ddos攻撃とは?基本的な仕組みと特徴
ddos攻撃(Distributed Denial of Service attack)は、多数のコンピューターから一斉に特定のサーバーやネットワークにアクセスを集中させ、サービスを利用できない状態に追い込む攻撃です。大量の通信で帯域やサーバー資源を埋め尽くすことで、正規ユーザーがアクセスできない状況(サービス不能)を引き起こします。
攻撃に利用される端末は、マルウェアに感染したパソコンやIoT機器などで構成された「ボットネット」であることが多く、攻撃者本人の所在を特定しにくい点が厄介です。また、攻撃は短時間で終わる場合もあれば、長時間・断続的に続く場合もあり、ビジネスへの影響は非常に大きくなります。

また、ddos攻撃は単体で行われるだけでなく、他の不正アクセスや情報窃取の「陽動作戦」として使われることもあるといわれています。実際の攻撃シナリオはケースごとに異なり、すべてを事前に予測するのは困難です。
- ddos攻撃は多数の端末からの大量アクセスでサービスを停止させる攻撃
- ボットネットを利用することで攻撃元の特定が難しくなる傾向がある
- 陽動として使われるケースもあり、被害はサービス停止だけにとどまらない可能性がある
ddos攻撃の主な種類と比較一覧
ddos攻撃と一口に言っても、実際には複数の手法があります。ここでは代表的な種類と特徴を一覧で整理します。実際の攻撃では、これらが組み合わされるケースも多くあります。
| 攻撃タイプ | 概要 | 主な狙い | 影響しやすい対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボリューム型攻撃 | 大量のトラフィックで回線帯域を埋め尽くす | ネットワーク回線の飽和 | Webサイト全般・ネットワーク回線 | 典型的なddos攻撃として頻出 |
| プロトコル攻撃 | TCP/UDPなどのプロトコルの弱点を突く | サーバーやFWのリソース枯渇 | Webサーバー・ファイアウォール・ロードバランサー | SYN Floodなどが代表例 |
| アプリケーション層攻撃 | HTTP/HTTPSリクエストを悪用し負荷を高める | アプリケーションの処理能力低下 | ECサイト・API・ログインページ | 正規リクエストに偽装しやすく検知が難しい |
| DNS/メールなど特定サービス攻撃 | DNSサーバーやメールサーバーを狙い撃ち | 名前解決やメール配送の停止 | インフラ系サーバー | 他サービスへの連鎖的な障害を引き起こす可能性 |
近年では、標的のサービス内容を理解したうえで、最も負荷がかかる処理を狙ってリクエストを集中させる高度な攻撃も増加していると指摘されています。そのため、単に帯域を増やすだけでは対処しきれないケースもあります。
- ddos攻撃にはボリューム型・プロトコル攻撃・アプリケーション層攻撃など複数の種類がある
- アプリケーション層攻撃は正規アクセスとの見分けが付きにくく、検知が難しい
- 自社サービスがどのタイプに弱いかを把握しておくことが対策の前提になる
DMM FXならサーバーの安定稼働を重視した取引環境で、投資を行いながらリスク管理の意識も高めることができます。
ddos攻撃による主な被害とビジネスへの影響
ddos攻撃の直接的な被害は「サービス停止」ですが、実際の損害はそれだけではありません。特にオンラインサービスを提供している企業にとって、短時間の停止でも売上や信頼に大きな影響を与える可能性があります。
想定される主な被害
- ECサイトや会員サイトの停止による売上機会の損失
- 金融サービスやオンラインゲームなどでの利用者離れ
- 障害対応・復旧対応にかかる人件費・外部コスト
- 長期化した場合のブランドイメージ低下・炎上リスク
- 攻撃と同時進行で行われる情報窃取・不正アクセスの可能性
特に、金融・決済サービスやFX・株式などのトレーディングサービスでは、数分の停止でも大きな機会損失やクレームにつながるおそれがあります。そのため、事前の対策や障害発生時の対応フローを整備しておくことが重要です。
- ddos攻撃の被害は売上損失・信頼低下・対応コストなど多方面に及ぶ
- 金融・決済サービスなどは特に停止時間の影響が大きい
- 事前のリスク評価と障害時の対応体制整備が重要な対策になる
ddos攻撃への基本的な対策と手順
ddos攻撃を完全に防ぐことは難しいとされますが、被害を最小限に抑えるための具体的な対策はいくつも存在します。ここでは代表的な対策と検討手順を整理します。
インフラ・ネットワーク面の対策
- 回線帯域やサーバーリソースの冗長化・スケールアップ
- クラウド型ddos対策サービスの導入検討
- CDN(コンテンツ配信ネットワーク)を利用した負荷分散
- ファイアウォールやWAFでの異常トラフィック検知・遮断ルール設定
運用・監視面の対策
- 攻撃兆候を検知するためのログ監視・アラート設定
- 障害対応フロー・連絡体制・外部ベンダーとの協力体制の整備
- 想定シナリオにもとづく訓練・復旧テストの実施
クラウド・外部サービスの活用
- 大規模トラフィックを吸収可能なクラウド基盤の活用
- ddos対策専用サービス(スクラビングセンター等)の利用
- DNSやメールなど重要サービスを冗長構成にする検討
- インフラ・運用・外部サービスを組み合わせて多層防御を構成する
- 事前に攻撃シナリオを想定し、復旧手順を整理しておくことが重要
- 自社だけで対応が難しい場合は専門ベンダーの支援を前提に設計する
個人・中小企業が今からできるddos攻撃対策のポイント
大企業ほど大がかりな対策が難しい個人や中小企業でも、今からできる現実的な対策はいくつかあります。自社の規模やサービス内容に応じて、優先度を付けて取り組むことが大切です。
中小企業向けの現実的な対策例
- レンタルサーバーやクラウドのddos保護オプションの有無を確認
- WAFやCDNサービスを利用し、アプリケーション層攻撃への耐性を高める
- 障害時の連絡先・復旧手順を簡易でもよいので文書化する
- 自社でサーバーを持たず、クラウドやSaaSを優先的に活用する
個人サイト・ブログ運営者の注意点
- 安価なサーバープランを利用している場合、ddos攻撃で長時間停止するリスクを認識する
- 攻撃が疑われる際は、自分だけで判断せずサーバー提供会社に相談する
- 重要なデータは定期的にバックアップし、最悪の場合に備える
- 自社の規模に合った現実的なddos対策を優先順位を付けて導入する
- レンタルサーバーやクラウドの標準機能・オプションを活用する
- 障害時に慌てないよう、最低限の手順書や連絡フローを決めておく
ddos攻撃対策とあわせて考えたいリスク管理とDMM FX
ddos攻撃は「システムの可用性リスク」を象徴するトピックですが、ビジネスや個人資産の世界では、相場変動リスクなどさまざまなリスクが常に存在します。ITリスクと同様に、投資や資産運用でも「最悪のケースを想定し、事前に備える姿勢」が重要です。
たとえばFXでは、相場急変時でもなるべく安定した取引環境を提供しているサービスを選ぶことが大切です。サーバーの安定性や情報配信のスピード、サポート体制などをチェックし、リスク管理の一環として口座選びを行うとよいでしょう。
DMM FXは安定した取引環境と豊富な情報提供で、リスク管理を意識した取引を目指す人にとって有力な選択肢のひとつです。
- ddos攻撃対策も投資リスク管理も「最悪シナリオを想定した準備」が重要
- 取引サービス選びではサーバーの安定性やサポート体制もチェックポイント
- DMM FXのような実績あるサービスを選ぶことで、リスク管理の選択肢を広げられる
ddos攻撃に関するよくある質問
ddos攻撃を完全に防ぐことはできますか?
現状、ddos攻撃を完全に防ぐことは難しいとされています。ただし、多層防御・クラウド型対策サービス・監視体制の強化などにより、被害を最小限に抑えることは十分可能です。自社のサービス規模や重要度に応じて、段階的に対策を導入していくことが現実的なアプローチです。
自社サイトがddos攻撃を受けているかどうか見分ける方法はありますか?
短時間でアクセス数が急増している、特定IPからのリクエストが異常に多い、特定ページに負荷が集中している、といった兆候があればddos攻撃の可能性があります。ただし、キャンペーンなど正常なアクセス増加と区別がつきにくいケースもあるため、ログ監視や専門ベンダーの支援を受けることが望ましいです。
中小企業でもddos対策サービスを使うべきでしょうか?
重要なオンラインサービスやECサイトを運営している場合は、規模にかかわらずddos対策サービスの導入を検討する価値があります。コストとのバランスを考えつつ、クラウド型のddos対策やWAF付きCDNなど、スモールスタート可能なサービスから試してみるのがおすすめです。